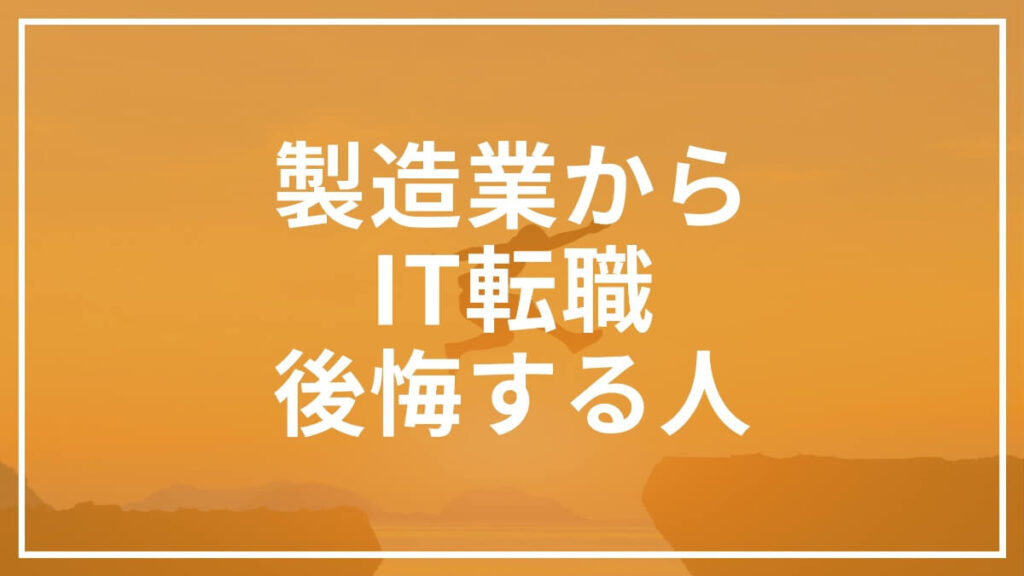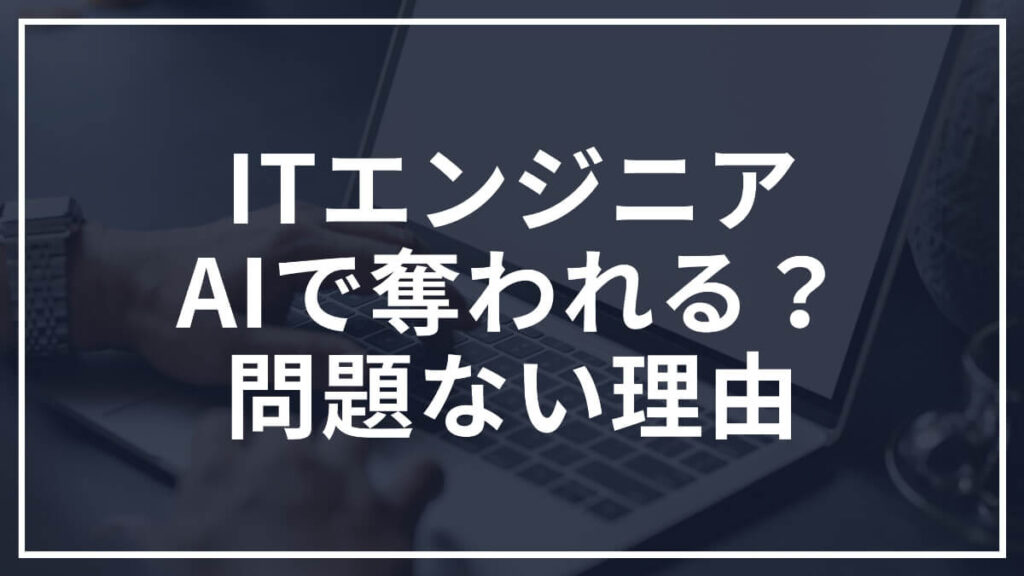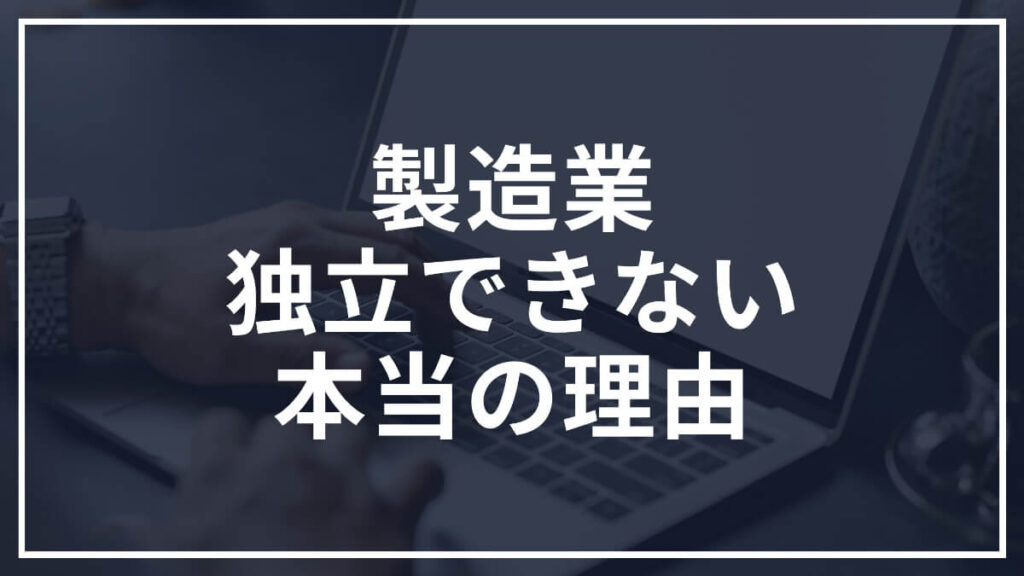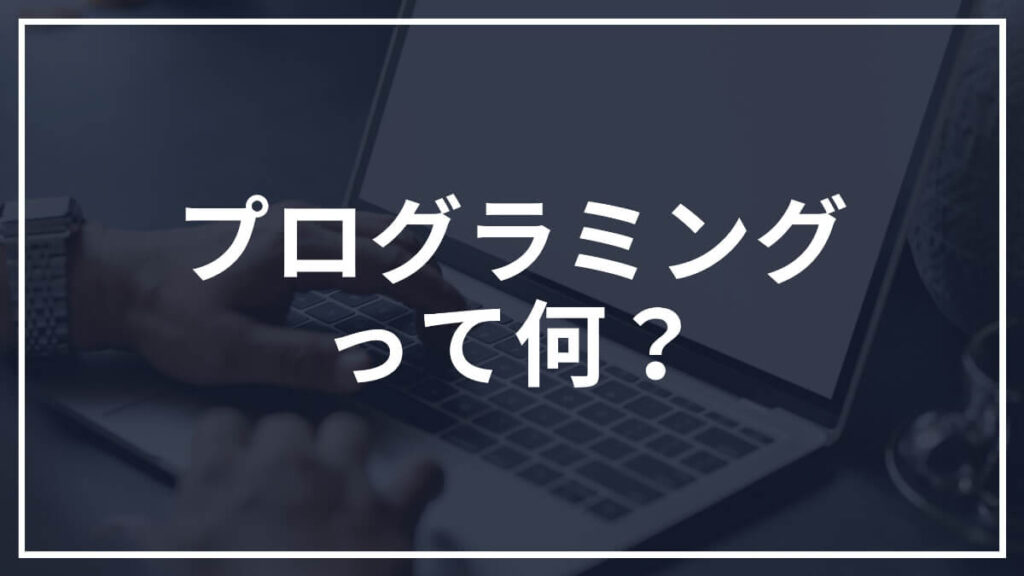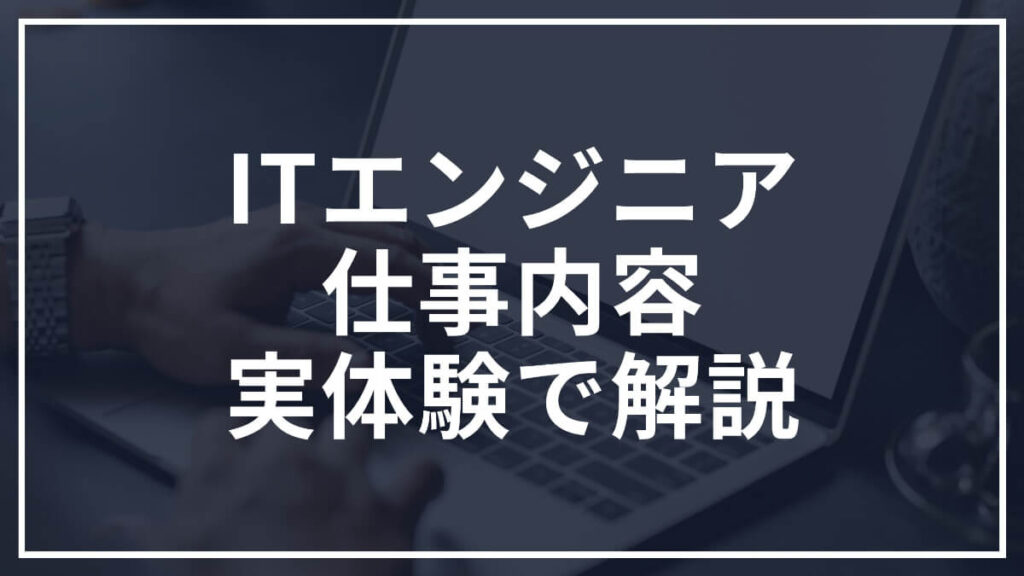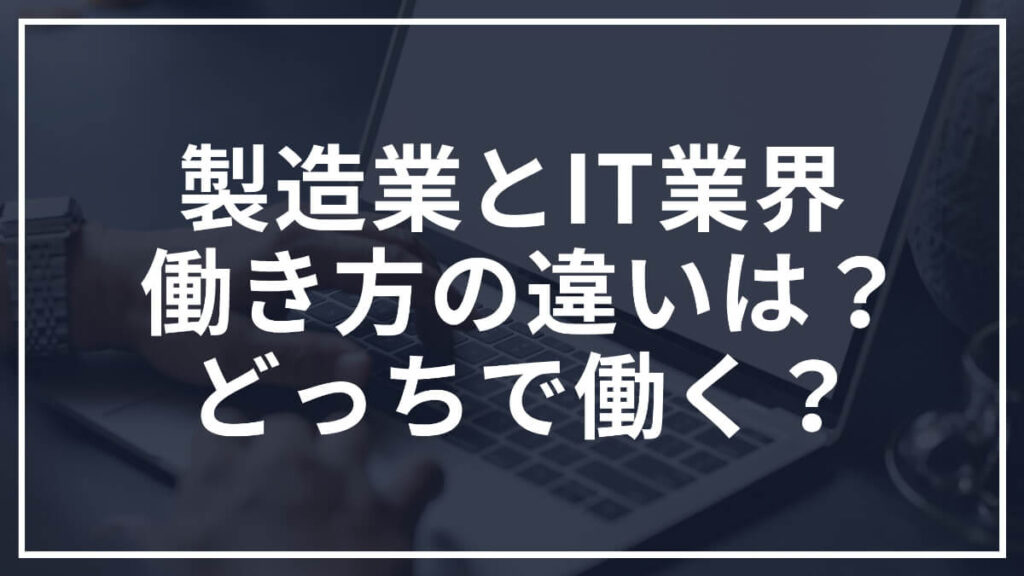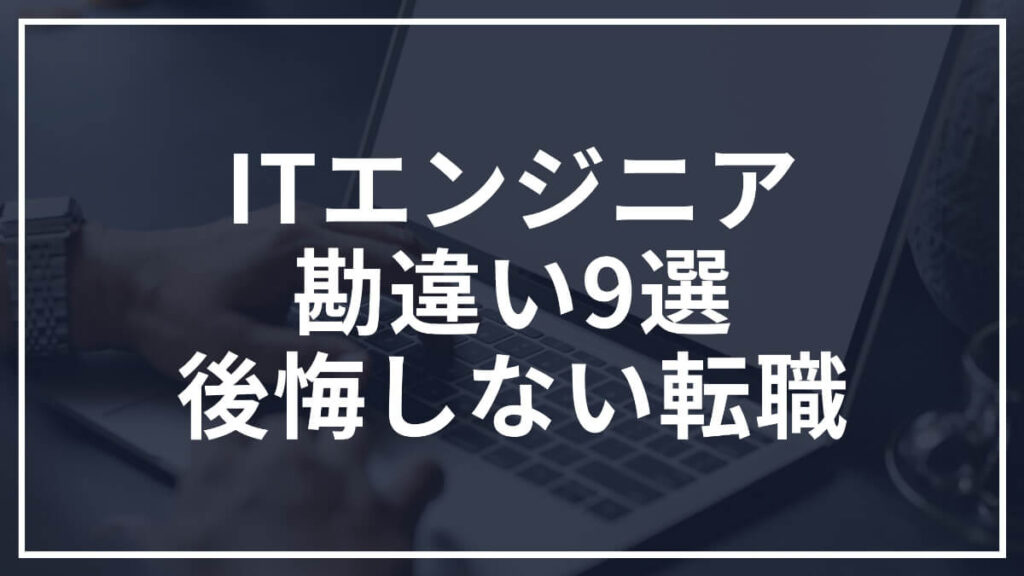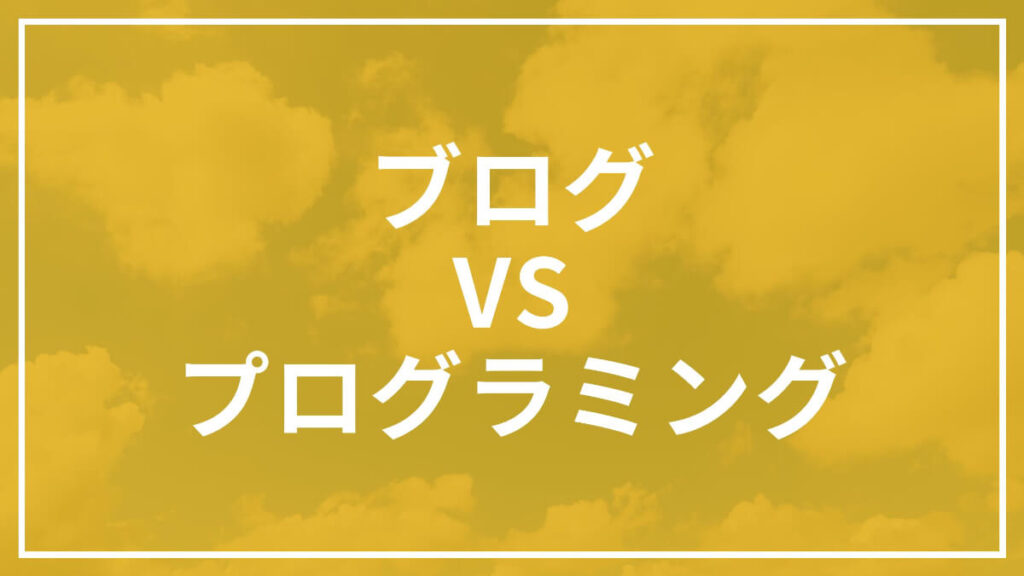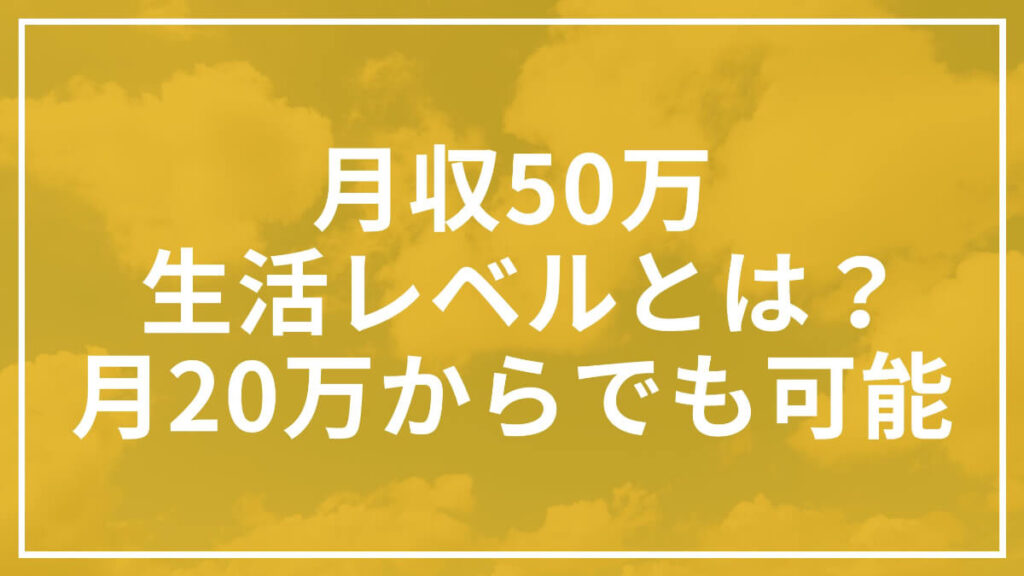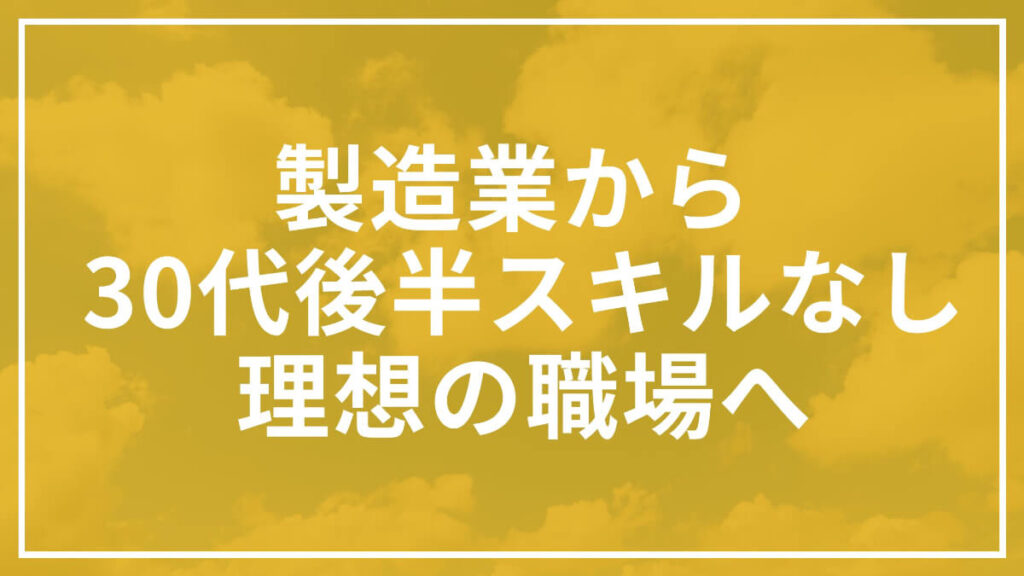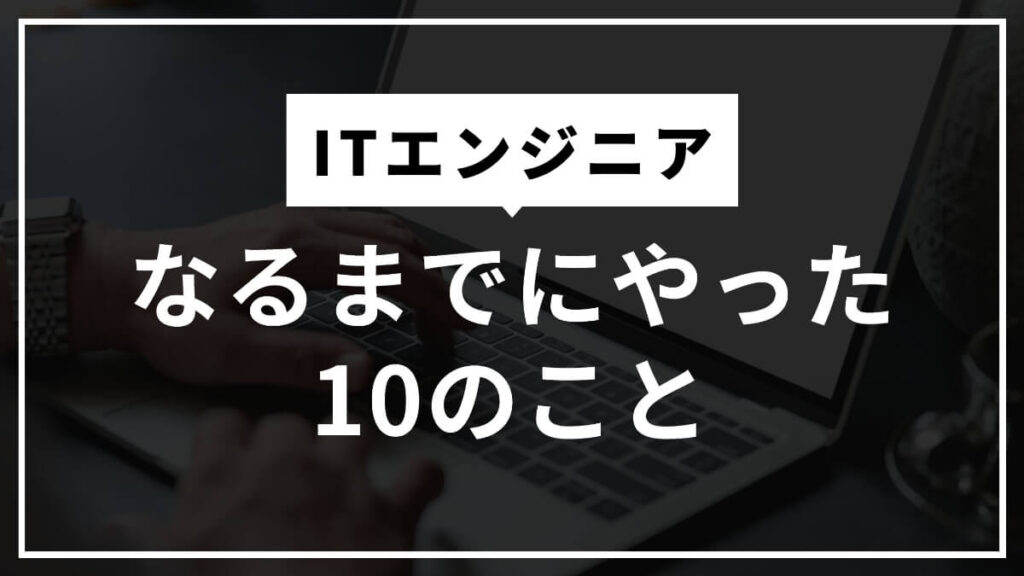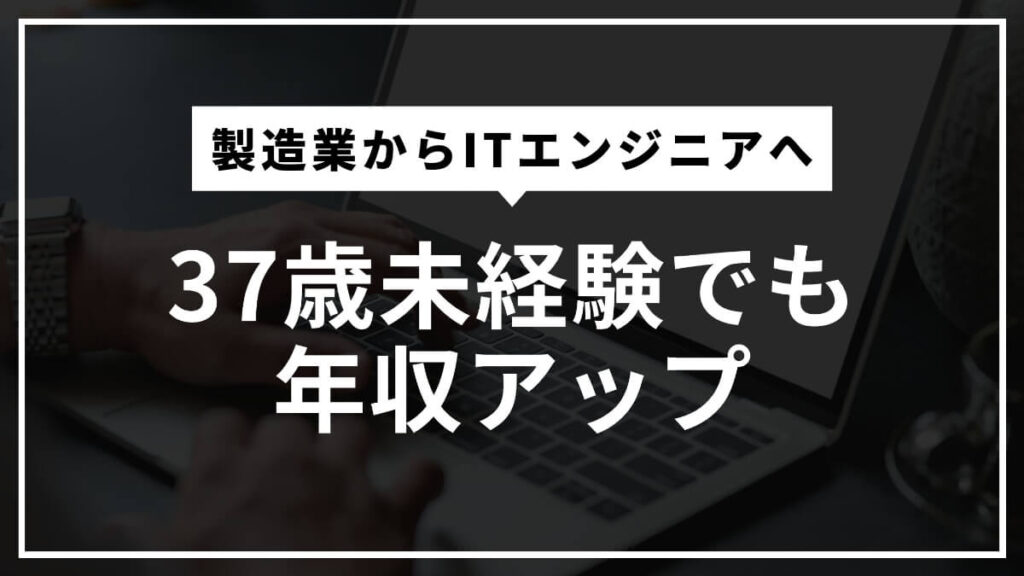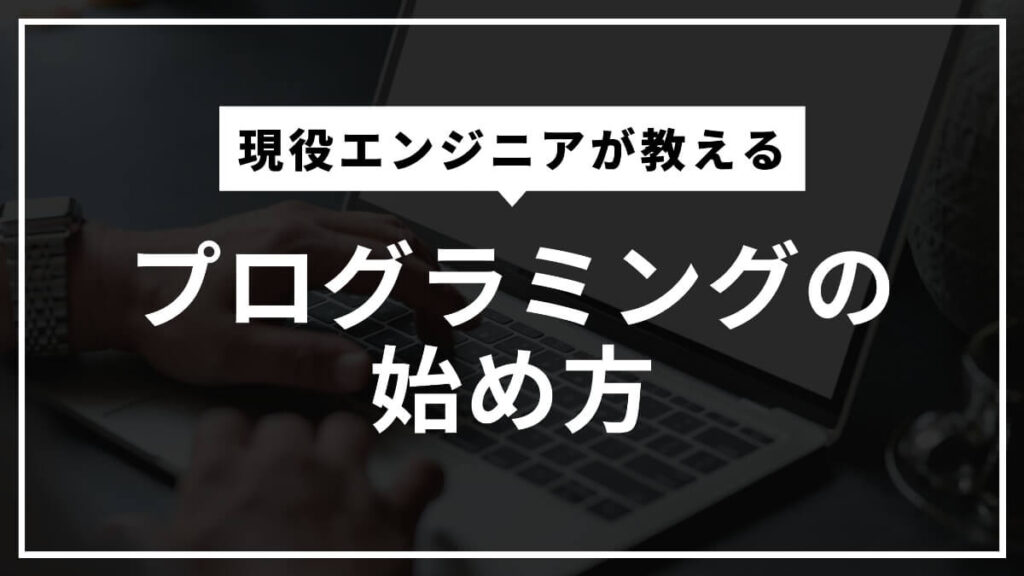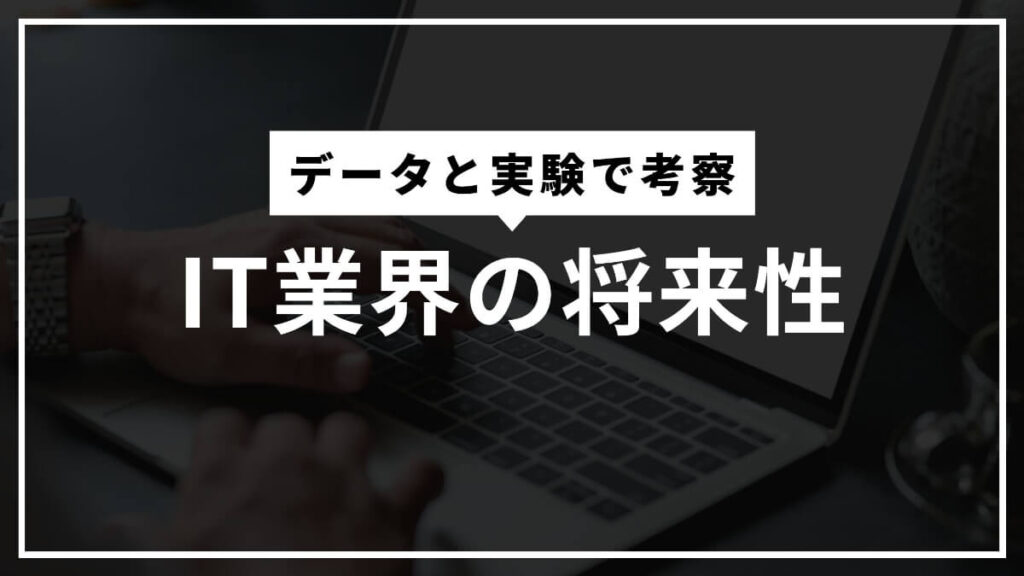-

製造業からのIT転職で後悔する人の特徴|未経験エンジニアの実体験
製造業からITエンジニアに転職を考えているが、後悔しないか不安 実際に製造業からITエンジニアに転職した人の体験談を知りたい 今の仕事を捨てて本当に正解なのか、失敗したくなくて怖い こういった悩みを解決します。 この記事を書いている僕は、製造業... -

ITエンジニアはAIで仕事を奪われるのか?これから目指しても問題ない理由
ITエンジニアの仕事って、AIに奪われるんじゃないのかな これからITエンジニアを目指しても、結局ムダになりそうだな 転職しても、「もう必要ない職業」と言われる日が来そうで怖い こういった疑問にお答えします。 僕は、製造業で10年以上働いた後、ITエ... -

僕が製造業では独立がイメージできず、ITエンジニアならできた理由
製造業で働いているけど、独立できるイメージが全然わかないなぁ 仕事を辞めてフリーランスになりたいけど、製造業じゃ無理なのかな? というか、自分には市場価値がないから無理なんじゃないか…と感じてしまう こういった疑問にお答えします。 僕は元々新... -

プログラミングって何?知るだけで日常が便利になる理由を現役エンジニアが解説
そもそも、プログラミングって何なんだろう? 便利そうとは聞くけど、仕組みや意味が分からない… なんか難しそうだし、自分にはあまり関係ない気がする こういった疑問にお答えします。 僕は現役のフリーランスエンジニアで、業界歴は5年です。元々は製造... -

ITエンジニアの仕事内容は3種類ある|未経験から転職した僕が実体験で解説
ITエンジニアの仕事内容って具体的に何をするんだろう? 興味があるけど、果たして自分でも業務をこなせるかな? 稼げるらしいけど、実際に働いている人の話を聞きたいな。 こういった疑問にお答えします。 僕は、製造業で10年以上働いた後、ITエンジニア... -

製造業とIT業界の違い|どちらで働くのが良いのか経験者が解説
製造業とIT業界の違いを経験者の視点で教えてほしいな ITエンジニアに興味があるけど、実際のところどうなんだろう? 結局のところ、製造業とITエンジニア、どっちで働くのが良いか教えてください こういった疑問にお答えします。 僕は製造業で10年以上働... -

未経験者がしがちなITエンジニアの勘違い9選|転職で後悔しないコツ
ITエンジニアに興味があるけど、現実の働き方や生活がわからない。 ネットではキラキラしたイメージがあるけど、実際のところどうなんだろう? 未経験から転職した人が実際に感じたギャップやデメリットを知りたい。 こういった疑問にお答えします。 現在... -

【経験談】ブログとプログラミング、どっちが稼げるか|本業にしよう
ブログとプログラミング、どっちの方が稼げるんだろう? 家庭や仕事がある中で、最短で収入を伸ばせる方法を知りたい 両方を経験した人から、最適な選び方を教えてほしいです こういった疑問にお答えします。 僕は、新卒から製造業で働いていて、プログラ... -

月収50万の生活レベルとは|月収20万から達成した方法も解説
月収50万円って、どんな生活レベルなんだろう? 実体験ベースで、本音の話を聞いてみたいなぁ。。。 あと、どうやって月収50万円を達成したのかも気になる 現在の僕はフリーランスエンジニアとして、月収50万円ほどを安定的に稼いでいます。 ただ、ほんの... -

【製造業向け】30代後半スキルなしから理想の職場へ転職する方法
30代後半でスキルも資格もない。この状態で転職なんて本当にできるのかな? 今の仕事に将来性を感じないけど、年齢を考えると下手に動くのも怖いし… 同じ状況から転職して、転職を成功させた人の方法や体験談を知りたいです。 こういった疑問にお答えしま...